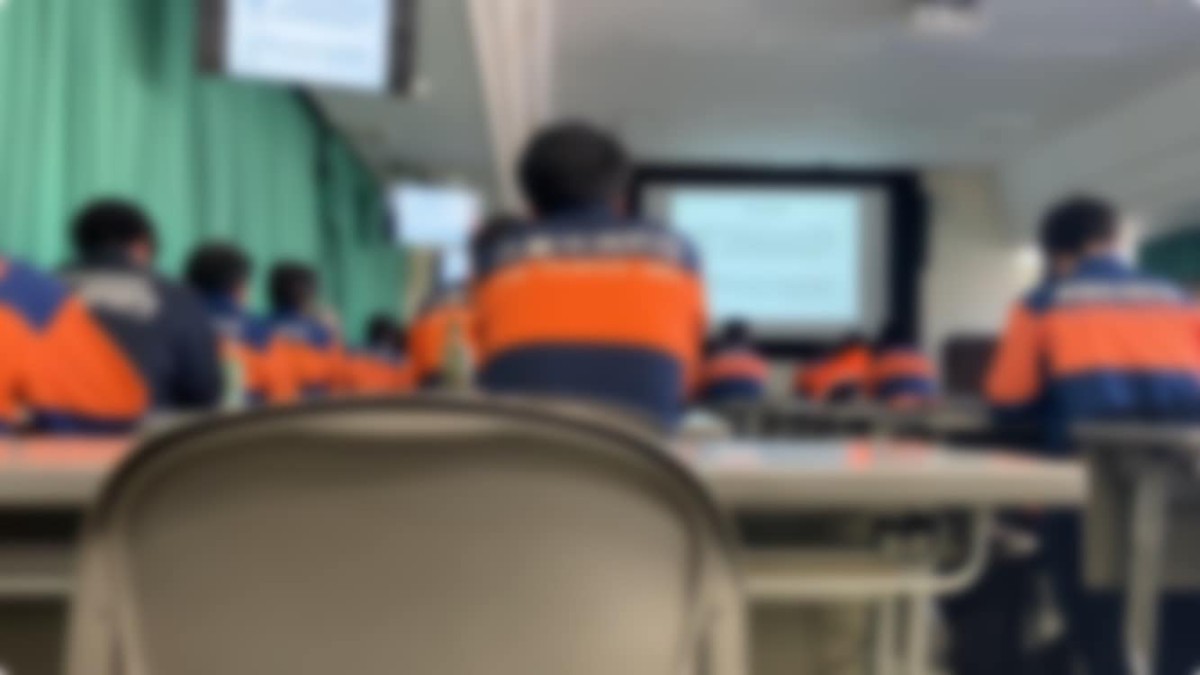
埼玉県消防学校で行われた消防団員基礎教育を受講
今日は消防団員基礎教育の受講のため、埼玉県消防学校へ。
講義の中で、消防団の活躍が大きく期待されるのは、大規模災害時だというお話がありました。東日本大震災の際には、本部消防組織は災害救助の目的地に行く前に、途中で呼び止められるなどして目的地になかなか到着できず、消防本部との連携のもと、地元の消防団員が地元の救助活動に大きな力を発揮したというお話を伺いましたが、広域災害の場合には、道路などのインフラが遮断されていたり、そもそも支援を求めるところが多すぎたりして、公的支援が行き届かないことがほとんどですので、やはり地域防災を担う消防団があることは有事において重要だと感じます。
また防災白書によれば、阪神淡路大震災の際に、生き埋めや閉じ込められた時の救助主体は、公助2割、共助8割だったそうで、特に広域災害時において公助に頼るのは限界があり、自助・共助意識の醸成は、地域防災力向上を図る上で永遠の課題だと言えそうでです。
このように有事において活躍が期待される消防団員ですが、昭和40年には全国で130万人いた消防団員も、今では76万人まで減少し、さらに会社員の比率が26.5%から73%となるなど、消防活動に参加できる人材の確保は数字以上に難しい状況になっているようです。
※久喜市では、消防団員確保のために、令和7年度の当初予算に団員個人への報酬見直しの計画を含めており、今議会で審議されることになっています。
そのような状況の中、そして日曜日にも関わらず、県内の自治体から消防団員約90名の方が、入校ガイダンス、職責と心構え、防災、緊急自動車運行管理、安全管理、そして修了式まで6時限みっちり受講。久喜市からも10名弱が参加されておりました。ご参加された皆様、大変お疲れさまでした。