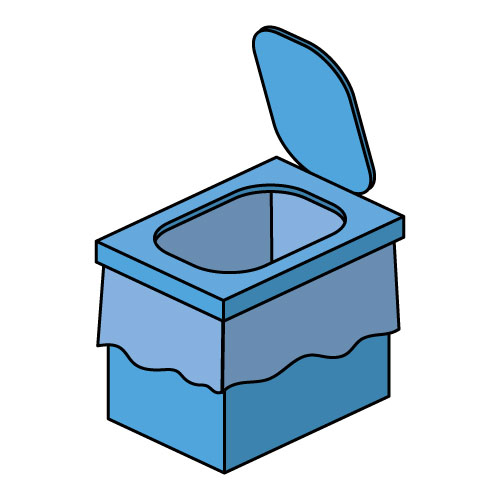
一般質問で災害時のトイレ確保に向けた対策の推進を要望しました
災害時におけるトイレ確保は、市民の健康と衛生を守る上で、極めて重要な課題です。特に避難所において、トイレ不足や衛生環境の悪化が深刻化することが多く、感染症の拡大や生活環境の変化、さらには不衛生なトイレを我慢した結果、エコノミー症候群の発症など、命に直結する災害関連死に発展することが分かっています。このようなことから、久喜市の災害時のトイレの備えに対する課題を洗い出し、対策を推進するべきと考え、一般質問をしました。一問一答形式で質疑のやり取りをご報告いたします。
(1)現在の久喜市の簡易トイレをはじめとするトイレ用品の備蓄状況とその試算根拠は。
現在携帯トイレ4万3,050回分、簡易トイレ1,848個、ラップ式トイレ102台、仮設トイレ111台を備蓄し、地域防災計画で想定する最大避難者数に応じたトイレの必要数量を確保している。災害時に必要とするトイレの備蓄数の考え方は、本市の最も大きな被害想定として、関東平野北西縁断層帯地震が発生した場合の最大震度7。その場合の発災直後の避難者数は2,590人、帰宅困難者が1万8,284人と推定している。この数値を基準とし、断水時にも使用できる使い捨てトイレの必要性について推計し、6万回分を備蓄の目標数に定めている。避難者数2,590人が1日5回、それを3日分で約3万9,000回分。それと、帰宅困難者1万8,000人強は1回分を想定しており、約1万8,000回分。それと、避難所の運営職員などの従事者に3,000回分で、合計6万回を目標としている。そして、現状は、携帯トイレ4万強と、それとラップポンの使い捨てを合わせますと6万6,000回以上保有しており、充足している。そのほかにお仮設トイレを111台備えており、また民間事業者との提携もしており、トイレの体制は確保されていると考えている。このほかに市民の役割もある。これは使い捨てトイレ最低3日分以上、推奨は1週間をお願いしている。そのような啓発、周知にも努めていきたい。
(2)1月26日に栗橋文化会館イリスで開催された「~トイレからはじめる防災~防災講演会」の動画を、市民に周知する考えはあるか。
現在ユーチューブにて公開している。講師からは、市民を対象に3月18日までの1か月間を条件に許可をいただいている。限られた期間だが、市民の皆様に災害時におけるトイレ問題について理解していただけるよう、周知に努めていく。
(3)災害時のトイレ設置及び清掃運用の方針を示すマニュアル等の整備状況は。
避難所におけるトイレ置に当たって配慮するべき事項や衛生的な環境を確保するための清掃など、その運用を定めた久喜市避難所運営マニュアルを整備している。またし尿の回収については、災害廃棄物処理計画の中で、し尿の発生量や、回収に必要なバキュームカーの数などをシミュレーションしている。
(4)市内事業者のトイレ保有数の把握状況及びトイレを保有する市内事業者との協定の締結状況は。
本市が締結する災害時応援協定のうち、トイレの供給に関する事業者は3社あり、そのうち2社は市内事業者。発災後、市から要請した場合に提供いただける仮設トイレについては、市外事業者から50台程度、市内事業者から40台程度の設置を見込んでいる。なお、そのうち市内事業者の1者からは、トイレカーの提供も可能となっている。