いじめ問題に、議員としてできること。
今日は、茨城県議会議員の秋山政明さんにお声がけいただき、いじめ問題を考える会議に参加しました。
私は、議員になる前の2020年に、日本財団HEROsの活動を通じて、いじめ問題に取り組んだ経験があります。当時はスポーツライターとしてHEROsの活動に参画し、アスリートの皆さんがいじめ問題に向き合う様子を取材しながら、社会に課題を提起し、考えや行動を促すきっかけを作ることが私の役割でした。
※日本財団HEROsの公式サイトで掲載した記事はこちらです。
https://note.com/segawa_taisuke/n/n9b1c76399e9f
しかし、現在は立場が大きく変わり、今回は地方議員として、いじめ問題にどのように取り組んでいけるのかを考える貴重な機会となりました。
文部科学省の最新調査(2024年度)によると、全国のいじめ認知件数は73万2,568件に達し、過去最多を更新しています。特に小学生の件数が突出しており、中学生、高校生、特別支援学校でも多くの事例が報告されています。いじめの内容も、身体的・精神的暴力、仲間外れ、ネット上での誹謗中傷など多様化し、深刻化しています。
特に、いじめが深刻化すると大きな社会問題となり、ニュースなどで報じられます。久喜市でも昨年、市内の小学校で「重大事態」が発生し、先日、その調査結果が公表されたことがニュースで報じられたばかりです。
いじめによる「重大事態」とは、いじめが原因で被害者の生命や生活に深刻な影響を与えたケースを指し、学校や教育委員会が特に慎重に対応しなければならない事態です。「いじめ防止対策推進法(2013年施行)」では、以下のような事例が「重大事態」に該当すると定義されています。
- 被害者が自殺や自殺未遂をした。
- 被害者が深刻な精神的・身体的被害を受けた(うつ病、PTSD、長期の怪我など)。
- 重大な物的損害が発生した(高額な金品を脅し取られるなど)。
- いじめを受けたことが原因で30日以上の長期欠席(不登校)になった。
このような事態が発生した場合、学校や教育委員会は速やかに事実関係を調査し、対策を講じる義務があります。
2024年度の重大事態の報告件数は1,306件であり、その約4割は学校がいじめとして認識していなかったケースでした。これは、学校がいじめの早期発見に十分対応できていないことを示しており、教育現場の対応力の強化が求められています。
では、なぜ学校側の対応が遅れてしまうのでしょうか。
本日の議論では、いじめが発覚した場合、学校は迅速な対応を求められるものの、「事態を大きくしたくない」という意識が働き、対応が遅れるケースがあることが指摘されました。また、保護者が相談しても、学校側が「いじめと認定されるまでは口外しないように」と対応を控えるケースもあります。さらに、いじめが発覚し教育委員会に報告が上がっても、「学校の対応を見守る」という消極的な姿勢にとどまり、積極的に介入しないことも多いようです。その結果、学校がいじめを「単なるトラブル」として処理し、対応を曖昧にしたまま不登校などの重大事態に発展するケースが見られます。
「重大事態(自殺や長期不登校など)」は、学校や教育委員会に報告義務がありますが、いじめの当事者にとっては非常にセンシティブな問題であり、また個人情報保護の観点からも公にされにくい傾向があります。そのため、結果的に学校や教育委員会の中で問題が留まってしまうことが多いと推察されます。
行政側は、相談窓口の設置やスクールカウンセラーの配置など、被害者支援の体制を整えています。しかし、「相談すると周囲に知られてしまうのではないか」「学校や教育委員会に知られることで不利になるのではないか」といった不安から、利用をためらうケースが少なくありません。また、相談窓口の認知度が低かったり、運営時間が限られていたり、スクールカウンセラーと学校教職員との連携が十分でないなどの問題があり、十分な効果が得られていないのが現状です。
いじめに関する情報は、当事者や保護者から学校、教育委員会へと流れるものの、適切な対応が取られるケースは少ないのが実情です。そのため、「議員がいかにしてこの情報の流れに関わり、学校や教育委員会に働きかけられるかが重要ではないか」というのが、今回の会議の主催者である秋山政明さんの設定したテーマでもありました。また、秋山さんは、いじめに関する情報を積極的に発信した結果、当事者から直接相談を受ける機会が増えたといいます。
私自身、議員になってから、当事者や保護者の方からいじめについて直接相談を受けたことは一度もありませんでした。しかし、秋山さんのお話を聞いて、それは私自身がいじめのSOS情報の流れの中に入ることができていなかったことも一因ではないかと考えるようになりました。
いじめに関する情報の流れに積極的に関わり、学校や教育委員会に対してマニュアルに沿った対応を促しながら重大事態の発生を未然に防ぐこと。そして、マニュアルの精度向上や支援相談の効果を高めるなど、久喜市に対して政策を提案していくことを目標に、取り組んでいきたいと思います。もし、いじめでお困りのことがございましたら、いつでもご連絡ください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


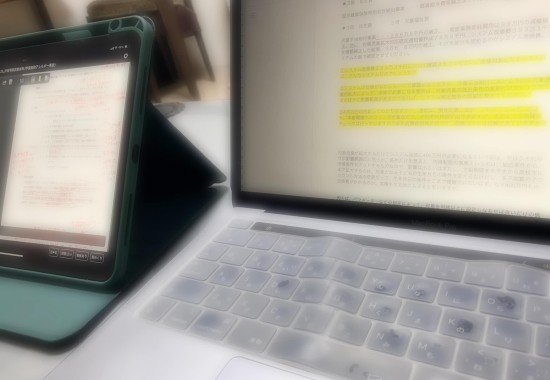




この記事へのコメントはありません。